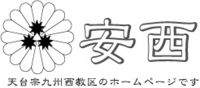※MEMBERページのIDやパスワードは主任鷲谷までお問い合わせください。メール
今月の法話
~節分~
鷲谷順照
節分は立春前日の季節の変わり目に行われる、鬼を祓って福を招く行事です。
鬼を外に追い払うことも大事ですが、心の中にある三毒「怒り、貪り、愚痴」に気づき、新しい年に新たな決意を持って一年を始める節目です。
鬼は外 鬼とは自分の心にいる鬼(煩悩)のことです。自分の三毒が最も恐ろしい鬼であり、それを豆(魔目、まめ)で滅することが豆まきの意味です。
福は内 鬼を追い払った後に、思いやりや感謝の心(福)が芽生えます。 あるところでは鬼も内というところがあるようです。
そういった行事を行うことで心の鬼(煩悩)を滅して、福の心で新しい一年を過ごせるように祈り、それを指針として生活していくことが「行」であり、実践していくことで素晴らしい一年になることでしょう。
令和7年度教区研修会
毎年恒例の教区研修会が令和7年8月29日久留米ニュープラザホテルにて執り行われた。75名ほどの参加があり盛会であった。
第1講
第1講は「子供の人権」という演題で真宗大谷派 光源寺住職 十時文雄師にご講義いただいた。小学生や中学生内での友達としての付き合い方、いじめに遭っている子供たちが出しているSOSを民生委員としてどう受け止めるか。いち早く対応出来るかということや、子供たちと共にひまわりを育てその種を風船に手紙を添えて付けて飛ばし、たくさんの方々と子供たちについて交流しながら子育ての応援をしていくお話をしていただきました。
第2講
第2講は「多様化する供養とお墓のかたち」という演題で礼拝空間デザイン室「TUNAGU」代表森口純一氏にご講義いただいた。最近の葬儀、供養、埋葬のかたちは多岐にわたり、多様化することで、寺院側といても様々な対応をしていかなければならないことを教わりました。
第3講
第3講は「災害時における自主避難のポイントセミナー」という演題でMS&ADインターリスク総研株式会社主任コンサルタント藤田草史朗氏ご講義いただいた。最近の地震や豪雨など甚大な被害が多発する中、寺院側といても様々な対応をしていかなければならないことを教わりました。
菅原道眞公御神前法要
光明供錫杖勤修
法儀声明研究会が出仕

令和7年2月25日太宰府天満宮本殿に於いて菅原道眞公御神前法要が勤修された。2月25日は道眞公の祥月命日にあたり、毎年九州教区の各部内寺院にて法要を勤修している。今年は法儀声明研究会の会員が担当し十数名の僧侶が参集した。仮本殿の天満宮にはたくさんの国内外の参拝客で賑わう中たくさんの参拝者の姿に道眞公がお喜びになられているかのようであった。
教学布教研究所所長川口一道師が導師に

コロナ禍が収束したくさんの参拝客で賑わう中、教学布教研究所川口一道師の導師の元、厳かに光明供錫杖法要が執り行われました。参拝に来られている方々もお参りの手を止め、その法要の厳かな音色に心を奪われているかのようであった。



伝教大師像建立5周年記念法要
伝教大師報恩法要
大般若理趣分転読
令和6年10月20日新上五島町荒川郷において伝教大師像建立5周年記念法要を厳修いたしました。

毎年させていただいておりますが、今年で5回目になりました。天候も荒れ模様でしたが、法要を始める頃には雲も晴れ、秋のちょっと強めの爽やかな風が私たちを包み清々しい法要となりました。大般若理趣分法要を厳修し、参詣された荒川郷の方々にお加持し、皆の健康と安穏を御祈願いたしました。
一隅大会を開催
5周年記念法要にあわせ町制20周年記念シンポジウムとして、一隅を照らす運動大会を開催しました。記念講演として三千院門跡門主小堀光實大僧正にお越しいただき「寄り添う心は尊し〜」という演題で講演していただきました。第2講として高橋弘一氏による講演、清興として上五島神楽保存会の皆様による舞の奉納がなされ300名ほどの聴衆の方々を魅了していました。

令和7年度年間行事のお知らせ
天台宗九州西教区宗務所長 嘉瀬慶文
謹 啓
教区内諸大徳の皆様には平素より教区行事に御協力賜り、誠にありがとうございます。
新型コロナウィルスは第5類になり全国的に様々なイベントが活発に行われるようになりました。
当教区といたしましても状況を見ながら安心して行事が行えるように取り組んでいく所存です。合掌
行事予定
-
対馬伝教大師像建立落慶法要 10月18日19日
一隅を照らす運動全国一斉托鉢 10月〜12月
藤光賢大僧正傳燈相承祝賀会 10月11月研修会 - 令和7年度教師選考会
- 令和7年度教区議会 令和8年3月
- 各種団体長会議 令和8年3月